
負の遺産(!?)、IE11にはいつまで対応する!?
我々Web開発者にとってMicrosoftのブラウザ「Internet Explorer」(以下「IE」)は悩みの種だった。
他のメジャーブラウザ Chrome、Firefoxなどと比べ、挙動(表示)が異なり Webサイトをリリース(公開)する際は、IEに対応するために わざわざ工数を割かなければならず、頭の痛い問題だった。
※IE10までは既にサポートが終了しているが、最終バージョンのIE11は 未だにサポート対象とされている。公式にはWindows10のIE11は「2029年1月」がサポート終了期限とされているようだ。。
Microsoftが2021年8月17日でMicrosoft 365でのサポート終了を発表
つい一ヶ月ほど前、Microsoftが2021年8月17日でMicrosoft 365でのサポート終了を発表した!
この情報に業界内は ざわつき色めき立った。(ちと大げさか…(笑))
「やっとIEの呪縛から解放される!」
が、よくよく見ると、単に「Microsoft 365」でのIEサポートが終了するだけで、IE11そのもののサポートが終了するワケではなさそうだ。。(涙)
なぜ 負の遺産とまで言われているIEが、ここまで延命されるのか?
それは、IEを動作保証ブラウザとして作られてきたシステムなど、レガシーがたくさん残っているからに他ならない。
省庁・自治体が提供するサービスや、銀行のオンラインシステムなども「IE11」での動作を前提に構築されているものが、まだ世の中にはウジャウジャある。
そのため、IEを完全に排除することができないのだ。
新規に作るものは排除しても構わない!?
そう考えると、IE11は レガシーシステムに対応するために存続しているのであり、「これから新たに作るWebサイト・システムは、IEを対象外にしても良い」と、ワタシは考る。
クラウドサービスで大きなシェアを誇るDropboxからも、以下の案内メールが来た。
誠に勝手ながら Dropbox では 2020年10月1日をもって、Internet Explorer 11 のサポートを終了させていただくことになりました。
Dropbox以外にも、IE11を対象外とするアナウンスが続々とされている。
IE11が 未だに存続している理由(レガシーに対応するため)を考えると、これから新規に作るものは、自信を持ってIEを対象外とすべきだと思う。
お客様には、きちんと理由を説明し、、「それでもIE11対応に。。」と言われるのであれば、そこは別途追加料金でも構わないと思う。
ホームページ制作のこと、ホームページの運営でわからないことや困っていることがありましたら、「株式会社アットライズ」までお気軽にご相談ください。
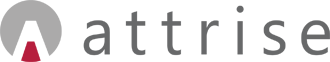
株式会社アットライズのホームページはこちら
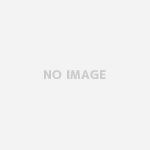

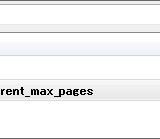






[…] 2020年9月17日に投稿したブログ「Internet Explorer 11のサポート終了」を読み返すと、 「公式にはWindows10のIE11は「2029年1月」がサポート終了期限とされているようだ」 と記載されているので […]