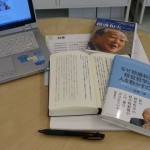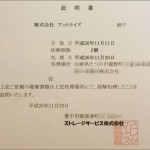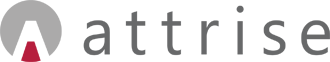大資本を持たない中小企業でも手軽に情報発信を!

創業への想い「前編:Web業界に転身した理由」に続き、後編を。
プロフェッショナルとしてのスキルを専門的に学ぶ
「西暦2000年問題」などという言葉がIT業界を騒がせていた頃、プロフェッショナルとしてのスキルを専門的に学ぶべく、クリエイター養成の専門学校「デジタルハリウッド」に通った。
そして2000年の9月、デジハリの同級生などからWebサイトの制作案件などを紹介され、仕事としてのサイト制作を手がけるようになった。(=創業)
ネットやメールを使った業務の性質もあり、自宅を作業場とする いわゆる「SOHO」というスタイルでの創業だった。
当時はまだ今のようなブロードバンドの常時接続などない時代。
ネットに接続するには電話回線のモデムを使って都度アクセスし、電話代を気にしながら急いでネットサーフィンし、回線を切る、、という使い方。
「自動巡回ソフト」なる、あらかじめ登録しておいたURLを自動的に巡回し速やかに電話回線を切断し、あとはキャッシュをゆっくり見る、、などという今ではあり得ないようなフリーソフトが重宝していた時代だ。
この頃、NTTが「テレホーダイ」という23時~翌8時までは定額で使えるサービスを提供しており、23時を過ぎると一斉にネットにアクセスしネットが重くなるなどの影響が出たなんてことも今では懐かしい。。
大資本を持たない中小企業でも手軽に情報発信を!
2000年9月に創業してから、2001年3月に法人化し「有限会社アットライズ」としてスタートすることになるのだが、その時の思い=創業の精神は、東芝クレーマー事件を目の当たりにし「自ら情報発信する側になりたい」との想いから、「大資本を持たない中小企業でも手軽に情報発信できるようにしたい」という想いに進化た。
以下、アットライズ経営理念の冒頭にも記載している創業者の想いです。
インターネットの進歩発展は、それまでのマス広告とは異なり大資本を持たない中小企業でも手軽にローコストで情報発信することが可能になりました。
アットライズは、このインターネットや関連するサービスを提供することで、より多くの企業とその顧客との繋がりを増やし、お客さま企業の発展と、お客さまに心から喜んでいただけるお手伝いをして参ります。
お客さまに「ありがとう」と言っていただけることがアットライズの一番の喜びであり、そのような企業活動を通して地域・社会に貢献していくことで、全従業員の物心両面の幸福を実現して参ります。
アットライズ(Attrise)、社名に込めた想い

名刺交換等でご挨拶させていただくと「アットライズという社名の由来はなんですか?」と聞かれることがある。
「アットライズ(Attrise)」は「引きつける、魅力」などの意味をもつ「attract」という単語と、「昇る、上昇する」などの意味をもつサンライズの「rise」を合わせた造語。
「魅力的で上昇志向の会社に」、との想いで名付けた社名です。
ちなみにこのとき拘ったのは、「五十音は『ア』で始まり、アルファベットは『A』で始まる」社名。
並び順として上位にくる方が何かと有利、という今で言うSEO対策と同じ発想です。(笑)